ビートルズの曲は1曲ごとに独自の輝きを放っていますが、実は「似た空気」をまとった曲をペアで聴くと、魅力が何倍にも広がります。今回は、代表曲から隠れた名曲へと自然に橋渡しする“おすすめペア”を5組ご紹介します。お気に入りの曲から、まだ出会っていない世界へ旅してみませんか。
Let It Be → Across The Universe
同じ空気をまとった2曲
ビートルズ後期を代表する二つの静かな名曲、「Let It Be」と「Across The Universe」。どちらも穏やかな佇まいを持ちながら、聴き手に届く感情の質は異なります。前者は嵐の中で差す一筋の光のように励ましを与え、後者は広がる宇宙の中で静かに受け止めるような瞑想を促します。続けて聴くことで、祈りと沈黙が交互に胸に残る特別な体験が生まれます。
Let It Be — 混乱期を照らす母の声
「Let It Be」はポール・マッカートニーが発想の核を得た個人的な出来事から生まれました。幼くして亡くした母メアリーの夢を見て、母が語りかける「Let it be(あるがままに)」という言葉が心に残ったことをポール自身が語っており、その体験が曲の核になっています。曲は1969年のセッション群の中で形を整え、1970年に同名アルバムとともに広く知られるようになりました。バンド内の緊張や活動の先行きが不透明だった時期に発表されたため、一部では「別れ」や「終わり」を象徴する曲として受け取られることもありましたが、ポール自身は慰めや希望の歌であると述べています。
音楽面では、過度に装飾しないピアノ主導の骨格に、コーラスやオルガン的な響きが重なってゴスペル的な温度を帯びます。こうした素朴さと荘厳さの混在が、個人的な慰めを普遍的なメッセージへと昇華させています。映画やライブでの象徴的な扱われ方もあり、曲は時代を超えて多くの人に寄り添ってきました。
Across The Universe — 宇宙へ漂うことば
一方の「Across The Universe」は、ジョン・レノンの詩的志向が色濃く出た作品です。作曲自体は1967〜68年頃に始まり、瞑想や東洋思想の影響を感じさせるフレーズ(例:「Jai Guru Deva Om」のような歌詞的挿入)が登場することでも知られています。歌詞は言葉そのものを音の要素として扱う詩的な構成で、イメージが連なっていくうちに、聴き手の内部世界を広げる性格を持ちます。録音面では、アコースティックな基調に残響やテープ的な加工が加わることで、時間や重力から解き放たれたような浮遊感が生まれます。
曲は複数のテイクや版が存在することでも興味深く、後年にアルバム用のアレンジが施された版が公式になった一方で、ジョンが好んだような素朴な初期テイクもファンの間で高く評価されています。言葉をそのまま宇宙に放つような、静謐でありながら内側に響く力を持った一曲です。
ふたつの曲を続けて聴くと見えるもの
この二つを続けて聴くと、「Let It Be」が外向きに差す希望の光なら、「Across The Universe」は内向きに広がる宇宙的な慰めであることが際立ちます。前者は困難や混乱の中で立ち上がるための励ましを与え、後者はそこに一歩下がって世界を俯瞰させる静けさをもたらします。言い換えれば、前者は手を差し伸べる母の声、後者はその手をゆっくりと離して空へ投げるような静謐さに近い。どちらも「受け入れる」というテーマを共有しますが、そのアプローチが異なるため、連続して聴くことで互いの輪郭がより鮮明になります。
おすすめの聴き比べ方
アルバムの流れで聴く:1970年のアルバム文脈で両曲を比較すると、時代の空気や制作状況が伝わりやすいです。
素朴なテイクと完成版を比べる:「Let It Be... Naked」など、装飾を外した版とフィル・スペクター的な仕上げを比べると、曲の核がより見えてきます。
歌詞を読みながら聴く:特に英語の語感を味わうと、ジョンとポールの異なる言葉遣いが際立ち、聴き方が深まります。
最後に
「Let It Be」と「Across The Universe」は、同じ時期の作品でありながら、祈りと瞑想という異なる方向から“受け入れる”ことを描き出しています。交互に耳を傾ければ、ビートルズ後期の精神性と音楽的実験が織りなす深い世界を、身をもって体感できるはずです。
Here Comes The Sun → Good Day Sunshine
太陽の輝きが続くプレイリスト
Here Comes The Sun — 春の訪れを告げる光
1969年のビートルズは、Apple Corpsの混乱や内部分裂に直面し、バンドとしての息苦しさが増していました。その中、ジョージ・ハリスンはふとした瞬間にポジティブな気持ちを得ます。エリック・クラプトンの家の庭で軽くギターを弾いたとき、長い冬の後に差し込むような光にインスピレーションを受けて、「Here Comes The Sun」のアイデアが生まれたと伝えられています。
イギリスに戻って6月に歌詞の大部分を書き、7月にはロンドンのEMIスタジオでレコーディングを再開。この時、アコースティック・コードの明るさに、初期のMoogシンセや強いリズムのビートが加わり、春の訪れる空気感を音で表現しています。曲全体の柔らかさと明るさは、聴けば春の訪れを肌で感じさせるほどで、ジョージの心にも重くのしかかっていた重圧を、光のように取り払ったような瞬間を伝えています。
Good Day Sunshine — 真昼の幸福感へ
一方、1966年にリリースされた『Revolver』収録曲「グッド・デイ・サンシャイン」は、ポール・マッカートニーが作曲した、明るく陽気な雰囲気を持つ曲です。
この曲は、具体的なインスピレーション源があるという説もいくつかありますが、ポール自身は特に特定の影響を挙げていません。一般的には、太陽の輝きや、晴れた日の幸福感をそのまま音楽で表現したいというポールの純粋なひらめきから生まれたとされています。
軽快で跳ねるようなピアノのリズム、ハッピーなコーラスが特徴的で、聴く人を一瞬で明るい気分にさせる、シンプルかつストレートな作品です。
イントロから軽快なリズムが弾むように続き、サビでは「Sunshine」という言葉が喜びそのもののように何度も繰り返されます。構造としてはポップで単純ですが、その分ストレートに「太陽があって僕は幸せだ」というメッセージが伝わり、聴く人の心を一瞬で明るく照らします。
2曲を続けて聴くと感じる“一日の流れ”
「Here Comes The Sun」は朝の光、忍び寄る春の訪れをそっと運んでくるようで、「Good Day Sunshine」はそのまま真昼のまぶしさと幸福感に包まれるような感覚です。どちらも“太陽”がテーマですが、朝の静かな目覚めと昼の高揚感という時間帯と感情の違いが明確に伝わります。
加えて作曲者間の対比も面白くて、ジョージの光への憧れや心の救済感情に対し、ポールのこれは文字通り“音で祝えばいい”という即時性ある喜びの表現との対比が、聴き比べを通じてより鮮明になります。
おすすめの聴き比べ方
春先の朝に組み合わせて聴く
朝の支度中に「Here Comes The Sun」、昼への切り替わりに「Good Day Sunshine」を流すと、一日の気分転換にぴったりな流れになります。時間帯のBGMとして並べて賑やかさ/余韻を楽しむ
静かな朝には前者を、夕方や午後のひと息には後者を。流れだけでなく、心の温度も時間帯と合わせて変わっていきます。
最後に
「Here Comes The Sun」と「Good Day Sunshine」は同じ“太陽”という共通のモチーフを持ちながら、朝の穏やかな希望と昼の爽快な幸せという対照的な世界を描いています。朝と昼の心の差を音楽として感じ取る体験は、ビートルズの繊細な表現力を改めて実感させてくれる贅沢な旅になるでしょう。
Eleanor Rigby → For No One
孤独というテーマを多面的に描く二つの名曲
Eleanor Rigby — 誰にも気づかれない孤独の物語
1966年にリリースされた「Eleanor Rigby」は、ビートルズの中でも特に異彩を放つ楽曲です。通常のバンド編成を捨て去り、弦楽八重奏というクラシック音楽の手法を大胆に導入したこの曲は、孤独というテーマを深く掘り下げています。
歌詞は、誰にも見向きもされずに日々を送るエリナー・リグビーという女性と、彼女を見守る孤独な神父マッケンジーの二人の姿を通じて、「孤立」や「忘れ去られた存在」の哀しみを描いています。決して派手ではないものの、日常の隙間に潜む切実な現実が、静かにそして強烈に胸に迫るのです。
この曲の作曲はポール・マッカートニーが中心ですが、ジョン・レノンもそのテーマ設定に影響を与えたといわれています。特筆すべきは、ジョージ・マーティンの弦楽アレンジの巧みさで、冷たくも繊細な弦の響きが歌詞の世界観を際立たせています。弦楽器の鋭い音色は、エリナーの孤独な人生を象徴するかのように響き渡り、聴く者に静かな衝撃を与えます。
歌詞の中で繰り返される「All the lonely people, where do they all come from?」という問いかけは、孤独という感情の普遍性を示しており、特定の人物だけでなく現代社会の誰もが抱える孤立感を暗示しています。
For No One — 静かに終わる愛の物語
同じく1966年の『Revolver』に収録された「For No One」は、ポール・マッカートニーが作詞作曲を手掛けた楽曲であり、こちらもまた孤独をテーマにしています。ただし、「Eleanor Rigby」が社会的な孤独を描いているのに対し、「For No One」はより個人的で恋愛の終わりを静かに見つめる内容です。
歌詞は、かつての恋人との関係が冷め切ってしまい、感情が完全に途絶えてしまった瞬間を淡々と綴っています。「彼女の瞳にはもはや愛の輝きはなく、涙の奥にさえも何も見えない」という表現が、その冷徹な現実を象徴しています。
音楽的には、ポールの繊細なボーカルに加え、クラヴィコードやアラン・シヴィルのフレンチホルンが用いられており、室内楽的な静けさと冷たさが曲全体を包み込みます。特にフレンチホルンの響きは温かさと哀愁が混じり合い、終焉を迎えた愛の余韻を感じさせます。
2曲を続けて聴く意味
「Eleanor Rigby」と「For No One」を続けて聴くことで、孤独というテーマの多面性を深く味わうことができます。前者は社会的・群像的な孤独であり、日常に埋もれてしまった人々の存在を示します。一方、後者は個人的・感情的な孤独であり、愛の終わりを静かに受け入れる様子を描いています。
両曲とも、感情を過度に表現することなく抑制された語り口で進むため、聴く者の想像力をかき立て、孤独の奥深さを静かに伝えます。特にポールのボーカル表現は、距離を置いたナレーターのような視点から、内面の痛みや寂しさを繊細に浮かび上がらせています。
また、どちらも典型的なバンドサウンドを離れ、室内楽的な編成が用いられている点も共通しています。これにより、孤独というテーマがより直接的に聴き手に届く構造となっています。
おすすめの聴き方
歌詞を読みながら聴く
英語の歌詞を理解したうえで聴くと、それぞれの曲が持つ孤独の色合いがより鮮明に感じられます。日本語訳と併せて聴くのも効果的です。『Revolver』アルバム内の位置関係にも注目
「Eleanor Rigby」はアルバムの2曲目に、「For No One」は10曲目に収録されており、アルバム全体の構成の中で孤独というテーマが繰り返し織り込まれていることに気づけます。感情の層を感じ取る
単に悲しいだけでなく、孤独の種類や深さの違いを感じ取りながら聴くと、新たな発見が生まれます。
最後に
「Eleanor Rigby」と「For No One」は、ビートルズの作品の中でも孤独を異なる視点から描き出した珠玉のペアです。社会的な疎外感と個人的な愛の終焉というテーマを通して、聴く者に人間の内面に潜む静かな哀しみを優しく教えてくれます。この二つの曲を続けて聴くことで、孤独の多様な側面を味わい、ビートルズの音楽的深みをより一層実感できるでしょう。
Strawberry Fields Forever → Lucy in the Sky with Diamonds
幻想世界への入り口としての「Strawberry Fields Forever」
1967年に発表された「Strawberry Fields Forever」は、ビートルズの実験精神を象徴する一曲です。ジョン・レノンが自らの少年時代の記憶、特に孤独と夢想を重ね合わせながら書き上げた作品であり、リヴァプールの孤児院「ストロベリー・フィールズ」を題材にしたことで知られています。歌詞には現実と空想の境界が曖昧に混じり合い、「本当の自分」と「外の世界」との距離感を表現する独特の詩情が漂っています。
音楽的にも特筆すべき点は多くあります。まず、プロデューサーのジョージ・マーティンとエンジニアのジェフ・エメリックの手による大胆な編集です。異なるテイクを物理的に接ぎ木し、キーやテンポの異なる録音を一つにまとめることで、楽曲全体に不安定で夢幻的な質感を与えています。また、メロトロンや逆再生テープ、インド音楽的な楽器の響きが加わり、当時のポピュラー音楽の常識を超えた音響空間を作り出しました。
この曲はジョン自身の内面世界を反映するものであり、「何が現実で、何が幻想なのか」をリスナーに問いかけます。聴き手は楽曲に没入することで、自らの心象風景を投影し、現実世界の輪郭がぼやけていくような感覚を味わうのです。
サイケデリック絵画のような「Lucy in the Sky with Diamonds」
「Lucy in the Sky with Diamonds」もまた、幻想的なイメージに彩られた作品です。ポール・マッカートニーの証言によれば、この曲の発想はジョンの息子ジュリアンが描いた絵に由来しています。絵の中には友人ルーシーと空、そしてダイヤモンドのモチーフが描かれており、それがジョンの想像力を刺激したといわれています。
楽曲は緩やかな三拍子のヴァースと、突如として開放感あふれる四拍子のサビという対比で成り立っています。ヴァースではオルガン風に加工されたロウリー・オルガンが神秘的な響きを生み出し、リスナーを夢の入り口へと誘います。そしてサビに入ると、一気にテンポが速まり、万華鏡を覗いたかのような鮮やかな光景が広がります。この構成は、幻想的な静けさから一気にサイケデリックな祝祭へと飛躍する劇的な体験をもたらします。
歌詞には「タンジェリンの木」「マーマレードの空」といった鮮烈でシュールなイメージが並び、聴く者を非日常の世界へと誘います。ジョンの詞は単なる描写を超え、聴き手自身の想像力を膨張させ、現実と幻想の境目を意識させるのです。
二曲をつなぐ幻想の糸
「Strawberry Fields Forever」と「Lucy in the Sky with Diamonds」は、どちらもサイケデリック期のビートルズを代表する作品ですが、単に同時期の産物という以上に深い共通点を有しています。両曲とも「現実世界を超えたもう一つの場所」を提示し、リスナーにそこへの入口を示しているのです。
前者はジョンの内省的で曖昧な現実感覚を反映しており、後者はカラフルで外向的な幻覚的世界を描きます。すなわち「Strawberry Fields Forever」が個人の心の中に閉じこもる幻想であるならば、「Lucy in the Sky with Diamonds」は心の外に拡張された幻想といえるでしょう。両者を聴き比べることで、ジョンの創作における内向と外向、静と動、曖昧さと鮮烈さという二面性が浮かび上がります。
また音楽的に見ても、実験精神にあふれたスタジオワークや奇抜なサウンドエフェクトの活用といった共通要素が際立っています。特にメロトロンの幽玄な響きと、加工されたオルガンの音色は、ともに「現実を超えた音響世界」を形作る道具となっています。
聴き比べの楽しみ方
この二曲を続けて聴くと、ビートルズがどのようにリスナーを幻想世界へ誘い込むか、その手法の違いが一層鮮明になります。最初に「Strawberry Fields Forever」を聴くことで、心は曖昧で流動的な夢の領域へと漂い出します。そして次に「Lucy in the Sky with Diamonds」を聴けば、その夢は一気に色彩を帯び、きらびやかな幻覚世界へと変貌します。まるでモノクロの映画から突然カラーフィルムに切り替わるかのような体験を得ることができるでしょう。
両曲の並置は、ジョン・レノンの想像力の広がりを示すだけでなく、ビートルズというバンドが音楽を通じて現実を超える感覚をどのように表現していたかを浮かび上がらせます。聴くたびに新たな発見があるこの組み合わせは、ビートルズの魅力の奥深さを改めて実感させてくれるのです。
Come Together → I Want You (She’s So Heavy)
怪しげなカリスマを体現する「Come Together」
1969年のアルバム『Abbey Road』の冒頭を飾る「Come Together」は、ジョン・レノンのカリスマ性とビートルズ後期のバンド・アンサンブルの粋を集めた一曲です。もともとはティモシー・リアリーのカリフォルニア州知事選キャンペーンのスローガンから発想を得たものでしたが、実際に完成した曲は政治色を脱し、より抽象的で神秘的な響きを持つ作品となりました。
歌詞はナンセンスで断片的なフレーズの連続ですが、それが却って強烈な印象を与えます。「Here come old flat-top」から始まるオープニングは、聴き手を一瞬で不穏で妖しい世界へと引き込みます。比喩や隠喩に満ちた歌詞は特定の意味に収束せず、聴き手自身の解釈を誘発する仕掛けとなっています。
演奏面では、ポール・マッカートニーのベースラインが曲全体を支配的にリードしています。跳ねるようでいながらも深いグルーヴを湛え、ドラムのリズムと絡み合いながら独特の緊張感を生み出しています。ジョンのヴォーカルは低く囁くように始まり、次第に熱を帯びていきます。ブルースに根ざした要素がありながら、当時のロックの範疇を超えた斬新さを放つこの楽曲は、アルバムの幕開けにふさわしい強烈な存在感を誇っています。
執着と欲望の渦を描いた「I Want You (She’s So Heavy)」
同じ『Abbey Road』に収められた「I Want You (She’s So Heavy)」は、ジョンの最も直情的で、かつ実験的な楽曲の一つです。その歌詞は極端に単純で、「I want you, I want you so bad」といった欲望の叫びが繰り返されるだけです。しかし、その単純さがかえって強烈な感情を生々しく伝えます。
楽曲構造は異例です。シンプルなブルース進行を基盤としながら、演奏は徐々に重苦しく、圧倒的な音の塊へと膨れ上がっていきます。ジョージ・ハリスンのギター、ビリー・プレストンのオルガン、そしてリズム隊が織りなすサウンドは、執拗に反復されることでトランス状態のような没入感を生み出します。特筆すべきは、楽曲の最後に延々と続くノイズ混じりのリフの反復であり、それが突然ぶつりと断ち切られるように終わる構成です。この唐突な終結は、聴く者に強烈な印象を残し、アルバム全体の流れにおける重要な効果を果たしています。
「She’s So Heavy」という副題が示すように、この曲は愛や欲望の甘美さよりも、その重苦しい側面を強調しています。ジョンがヨーコ・オノに抱いた激しい感情がそのまま音楽化されたと解釈することも可能であり、ビートルズの他の楽曲には見られないほど直接的なパッションが刻まれています。
二曲を貫くダークな磁場
「Come Together」と「I Want You (She’s So Heavy)」は、アルバム『Abbey Road』において互いに響き合う存在です。前者は妖しいリーダー像を提示し、後者は抑えきれない欲望を音楽化する。いずれも光よりも影を強調したジョンの作品であり、アルバムに濃厚な陰影を与えています。
音楽的にも両曲はブルースの影響を基盤としていますが、アプローチは対照的です。「Come Together」がクールで抑制されたグルーヴを展開するのに対し、「I Want You (She’s So Heavy)」は情念をむき出しにして音の洪水を築き上げます。つまり二曲は、同じ源流を持ちながらも「抑制」と「爆発」という両極を体現しているのです。
また、ジョンのヴォーカル表現も比較する価値があります。「Come Together」では低い声で呟くように始まり、謎めいたカリスマ性を醸し出します。一方「I Want You」では感情が剥き出しとなり、欲望の重みがそのまま声に込められています。この二曲を並べて聴くことで、ジョンの表現がいかに多面的であったかが浮かび上がります。
聴き比べの楽しみ方
この二曲を続けて聴くと、『Abbey Road』におけるジョンの存在感がいかに大きいかを実感できます。アルバム冒頭の「Come Together」はクールで知的な魅力を持ち、リスナーを惹きつけます。そこから「I Want You (She’s So Heavy)」へと移行すると、冷静な表情が次第に崩れ、欲望と執着の渦に呑み込まれていくような感覚を体験できます。これは単なる楽曲の並びではなく、一人の人間の心の内側を順に覗き込むような流れであるともいえるでしょう。
『Abbey Road』はしばしばポール・マッカートニーの音楽的手腕が光るアルバムと評されますが、ジョンの楽曲が放つ強烈な磁場もまた欠かすことのできない要素です。「Come Together」と「I Want You (She’s So Heavy)」を対で聴くことで、ジョンがいかにしてビートルズの音楽に陰影と深みを与えたのか、その本質を理解することができるのです。
ビートルズを“組み合わせ”で楽しむ贅沢
ビートルズの楽曲は、それぞれ単独で聴いても魅力的ですが、2曲を組み合わせて聴くことで新たな発見が生まれます。今回取り上げた5組のペアは、作曲者やアルバム、テーマに共通点を持ちながらも、異なる表情を見せる好例です。
「Let It Be」と「Across The Universe」では、救済と宇宙的静謐という精神性の異なる祈りが響き合い、「Here Comes The Sun」と「Good Day Sunshine」では、同じ“太陽”を題材にしつつ温度感の違う光景が描かれます。「Eleanor Rigby」と「For No One」では、孤独や失われた愛が室内楽的なアプローチで表現され、「Strawberry Fields Forever」と「Lucy in the Sky with Diamonds」では、幻想世界を異なる色彩で具現化しています。そして「Come Together」と「I Want You (She’s So Heavy)」では、グルーヴを軸にしつつ冷徹さと熱情が対照を成します。
これらのペアは、ビートルズが同じ素材やテーマから全く異なる音楽的景色を描く才能を示し、その創造性こそが今なお多くの人を魅了し続ける理由といえるでしょう。
以上です。ありがとうございました!

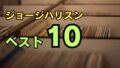

コメント