ビートルズといえば「明るく楽しい!ポップで元気いっぱい!」というイメージが先行しがちですが、現役時代の彼らは大人の眉をひそめさせるほど攻めた表現を次々と繰り出していました。パンクやハードラップに比べると「安心・安全の信頼ブランド」と思われがちですが、そんな楽曲は氷山の一角にすぎません。キリスト教に喧嘩を売る歌詞から、怪しい薬や性、狂気までも感じさせるサウンドまで──影響力の大きさゆえに、ある意味で世界で最も危険なロックバンドとも言えるでしょう。ここでは、そんな“危ないビートルズ”が生み出した放送禁止楽曲を厳選してご紹介します。
A Day in the Life 幻想的すぎて放送禁止
放送禁止第一曲目は「A Day in the Life」です。この曲は、1967年6月1日にリリースされた『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の最終トラック。ジョン・レノンが当時の新聞記事をもとに書いた歌詞で始まり、事故や日常の断片を断章的に並べる詩的手法が印象的です。中間部ではポール・マッカートニーによるメロディが挿入され、二人の対照的な創作スタイルが交錯します。さらに、約40名のオーケストラが不協和音のクレッシェンドを織り交ぜ、終始揺らぎを感じさせる音響空間を演出しました。この曲は短い構成ながら、新聞的リアリズムとサイケデリアが融合し、ポップソングの枠を越えたアートピースとして高く評価されています。
当時の社会・文化的背景
1967年、「サマー・オブ・ラブ」の時代です。若者たちがサイケデリック文化に夢中になった時代。アメリカ西海岸を中心にドラッグ文化が広がり、音楽にも大きな影響を与えていました。そんな中、ビートルズはこれまでのポップなスタイルを脱ぎ捨て、実験的なアルバム作りに乗り出します。ジョンとポールは社会への批判や自分たちの内面を同時に表現できる新しい曲作りに挑戦しました。
当時のイギリスでは、若者の反体制的な動きをマスメディアが厳しく監視していたため、ビートルズの実験は注目とともに批判も集めました。レコーディングでは、テープを繰り返し再生する「テープループ」や、音を逆さまに流す「逆再生」、声や楽器を何度も重ねる「マルチトラック録音」といった、当時としては珍しい技術を駆使して、まったく新しい音の世界を切り開こうとしたのです。
放送禁止の真相
「A Day in the Life」がBBCで一時的に放送禁止となった主な理由は、〈I'd love to turn you on〉というフレーズでした。当時の英語圏では「turn on」が薬物使用による"精神的覚醒"を示すスラングとして解釈され、BBCはこれが公共放送の価値観に反すると判断したようです。1960年代後半、英国では若者文化と薬物使用への懸念が高まっており、メディアはこうした内容に敏感になっていました。
「turn on」という言葉にはジョンもポールも意図的に使用したと認めています。こうした攻めたワードに加えてあのオーケストラです。不協和音クレッシェンドは、聴く者を幻覚状態に誘ってきます。言葉のみならず“音そのもの”が「いけない薬物」を連想させますね。
ただ、BBCのこの曲への放送禁止措置は、数週間程度で解除されたようです。これは、当時のメディアと若者文化との摩擦を象徴する出来事だったのかもしれません。音楽表現の自由と検閲の境界線を浮き彫りにした楽曲という意味でも「A Day in the Life」はすごい曲なのです。
「A Day in the Life」の影響
「A Day in the Life」はリリースから半世紀以上を経ても、その革新性とアート性が色褪せません。現代ではドラッグや検閲にまつわる解釈を超え、音楽的実験の象徴として多くのミュージシャンに影響を与え続けています。曲の構造美と詩的世界は、アルバム全体を締めくくるにふさわしいクライマックスとなり、今なおリスナーに鮮烈な余韻を残し続けています。
Happiness Is A Warm Gun 公序良俗に反するので放送禁止
放送禁止第二曲目は「Happiness Is A Warm Gun」です。この曲は、『The Beatles』(通称ホワイト・アルバム)における異色の一曲です。そのタイトルは、銃器雑誌『American Rifleman』に掲載されていた記事のキャッチコピーを拝借したもの。人の手に残る“熱を帯びた銃”に一種の官能性を見出す大胆な比喩です。
ホワイトアルバム収録の「Happiness Is A Warm Gun」は、アルバム全体を貫く創造的な雰囲気を象徴するナンバーですね。シングル化こそされなかったものの、後期ビートルズの代表作といっても過言ではないでしょう。約2分45秒前後という短い時間の中に、3つの異なるパートを組み合わせた独特の構成となってるのが特徴です。
レコーディングはEMIスタジオ(現在のアビー・ロード・スタジオ)で行われました。ジョンの特徴的なギターリフから始まり、続く中間部では「I need a fix」というフレーズを繰り返す不規則なリズムのセクションが展開します。そして最後は4拍子のドゥーワップ風の部分となり、ジョンの歌声とポールとジョージによるバッキングボーカルが印象的です。リンゴ・スターのドラムも全体を通して重要な役割を果たしています。
なぜ放送禁止になったのか
1968年の末頃、英国の国営放送BBCは「Happiness Is a Warm Gun」を公共の電波から外しました。最も大きな理由になったのは、ジョン・が歌う〈When I hold you in my arms… on your trigger〉という一節。ここで「on your trigger(引き金の上で)」は、銃を引く仕草を暗示しつつ、同時に官能的な場面を連想させると受け止められ、「性的なイメージが強すぎる」と判断されました。いわゆる公序良俗に反するってやつです
また、曲の中間部にある〈I need a fix〉というフレーズもドラッグ使用を思わせるスラングと見なされたため、非公式ながら問題視されていたようです。ただまあ、公式的には「性的な想像を過度に刺激する歌詞」というのが問題だったようです。ジョンもその点は、後年のインタビューはっきり認めています。やっぱり意図して、公序良俗に反したようです。
I Am the Walrus やっぱり公序良俗に反するので放送禁止
放送禁止となった三番目の曲は「I Am the Walrus」です。ビートルズならではのナンセンスが全開のこの曲は、1967年のサイケデリック・ムーブメント全盛期に発表され、言葉と音楽の境界を大胆に曖昧にした実験作です。ジョンレノンセンス炸裂なこの楽曲、〈I am he as you are he as you are me and we are all together〉などの反復詩句で聴き手をミステリアスな世界へ誘います。複雑に重ねられた管弦楽アンサンブルと逆回転テープが生み出す幻想的なサウンドは、言葉の意味を超えた“感じる”体験をリスナーに突きつけます。
意味不明な歌詞が意味するもの
「I Am the Walrus」は1967年11月24日にシングル「Hello, Goodbye」のB面として発表され、同年12月8日には英国で2枚組EP『Magical Mystery Tour』にも収録されました。当時ビートルズは『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』で切り開いたサイケデリック路線をさらに推し進める局面にあり、本作もまさにその象徴といえる一曲です。
制作のきっかけは、ジョンがどこぞの誰かが「自分の書いた歌詞を分析している」と知ったことにあります。ジョンはその話を受け止め、「それならば」ということで、わざと意味不明な歌詞を書いたのだとか。これきっかけで、この曲には意味のとれない言葉やイメージが次々と織り込まれていきました。
レコーディングにおいては、ストリングスやブラスセクションに加え、合唱団やBBCラジオドラマ『リア王』の台詞をテープ操作によって楽曲に重ねるといった手法が取られました。これにより、重層的で混沌とした音響世界が構築され、「I Am the Walrus」はビートルズの楽曲の中でもとりわけ異彩を放つ実験的なナンバーとして位置づけられています。
なぜ放送禁止になったのか
問題だとされたのは、「Let your knickers down」という歌詞です。一見すると何気ないこのフレーズですが、当時のイギリスにおいて、下着を脱ぐという性的な行為を連想させる可能性を孕んでいたようです。公共放送のBBCは、その曖昧な表現が聴取者に与える影響、特に子供たちへの影響を懸念し、放送コードに抵触すると判断したようです。
また、歌詞全体に漂う意図的な意味の不明瞭さも、もしかすると、放送禁止の決定を後押ししたのかもしれません。脈絡のない言葉の羅列とサウンドが醸し出す不気味な雰囲気は、公共の電波に乗せるには不適切であると判断されてもおかしくないわけです。ジョンのソロ楽曲「Mother」もそんな感じの理由で放送禁止を喰らっています。放送局は、芸術的な表現の自由よりも、公共の秩序と善良な風俗を守らなければならないのです。
放送禁止となったものの、「I Am the Walrus」はビートルズのレパートリーの中でもトップクラスの人気を誇る楽曲です。その先鋭的かつ幻想的なサウンドは時代を超えて聴き継がれています。
The Ballad Of John And Yoko 炎上覚悟だったので放送禁止
放送禁止第四曲目は1969年5月30日に発売された「The Ballad Of John And Yoko」です。この曲は、ジョンが中心となって制作した楽曲で、彼とオノ・ヨーコの結婚から新婚旅行までの出来事をそのまま歌詞にした、いわば“ジョンとヨーコの旅日記”のような一曲。ビートルズの楽曲では珍しく、非常に個人的でリアルな内容が盛り込まれている楽曲です。
この曲は、この時期としては珍しくポールとジョンの二人だけで録音されたことでも知られています。ジョージとリンゴは参加しておらず、リードギターからベース、ピアノ、ドラムまで、すべてをジョンとポールが分担して演奏しています。
なぜ放送禁止になったのか
「The Ballad Of John And Yoko」が放送禁止になった最大の理由は歌詞です。歌詞にキリストを登場させたこと、それから、「はりつけ」を想像させる「They’re gonna crucify me」といっているところです。宗教的感情を損ねる恐れがあるとして問題視されたのだと思います。これにより、イギリス国内のBBCをはじめ、多くのアメリカのラジオ局でも同曲の放送が見送られ、リリース直後のチャート動向や世間の注目度にも影響を及ぼしたようです。
それにしてもジョンレノン。1966年にキリスト教関連で大炎上させた実績があるにも関わらず、こういう歌詞を書いてしまっています。反省していないといいますか、炎上上等!だったのか、やっぱりすごい人です。それにしても、レコーディング時にポールは何もいわなかったのでしょうか。
この曲、放送禁止を受けたものの、シングルセールスで全英チャート1位を獲得しています。さすがにアメリカでは1位とはなっていませんが、ヨーロッパのキリスト教圏内の国々でも1位を獲得しています。個人的には、これが結構衝撃です。
ちなみに南アフリカでは、放送禁止どころの騒ぎではなかったようです。この曲きっかけで、ビートルズの作品の販売と放送が全面的に禁止されたようです。さすがに1970年にその規制は解除されたようですが、なんともまあ、恐ろしいですね。でも、ジョンのソロ作品はその後も規制されていたのだとか(今はどうなっているのか知らないけど)。
Come Together コカコーラがダメなので放送禁止
第五曲目は「Come Together」です。ビートルズ後期を代表する一曲と言っていいかもしれない楽曲です。この曲も放送禁止措置を喰らっているんですねー。不朽の名作『Abbey Road』のオープニングナンバーがまさかの放送禁止楽曲。だからビートルズは面白いのです。
選挙キャンペーンソング!?
ジョンがこの曲を書いたきっかけは、ティモシー・リアリーが1969年のカリフォルニア州知事選挙に立候補を表明したときの応援ソングを依頼したことです。ティモシー・リアリーとは、LSDなどのサイケデリック薬物の研究・普及で知られるハーバード大学の心理学者です。当時、ジョンとヨーコはモントリオールで2度目のベッド・イン(平和を訴えるパフォーマンス)を行っており、リアリーはその訪問者の一人でした。
リアリーは「Come together – join the party」というキャッチフレーズを掲げていて、それがインスピレーションの源。デモ版は短いフレーズを繰り返すだけのものだったようです。結局、リアリーは選挙運動中に逮捕され、選挙のためのキャンペーンソングにはならなかったのですが、リアリーきっかけで作成した短いでもが「Come Together」へと発展していきました。
なぜ放送禁止になったのか
BBCが放送禁止としたのは、ずばり「コカコーラ」という商品名が歌詞に登場するからです。国営放送であるがゆえですね、納得です。それにしても、今ままでの楽曲の放送禁止理由がハードだったため、なんとなく理由がライトに感じてしまいます。
Being For The Benefit Of Mr. Kite! 馬が理由で放送禁止
第六曲目は、「Being for the Benefit of Mr. Kite!」です。1967年6月1日に発表されたアルバム『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の中でも、この曲は特に異彩を放つ一曲です。ジョンが19世紀のサーカス団の古いポスターをアンティークショップで見つけ、その宣伝文句をほぼそのまま歌詞に取り入れたことで生まれたこの曲は、サーカスの華やかさとどこか懐かしい浮遊感が同居しています。当時のサイケデリック・ムーブメントにおける、日常の広告やチラシを音楽に変える斬新な試みとしてリリース当時から大きな話題を呼びました。
録音は1967年2月下旬。この時にあの有名はジョンのむちゃぶり「おがくずの匂いがするサウンドにしたい」が飛び出します。こまったジョージマーチン。彼が取った手法は、パイプオルガンを録音したテープをほんの数センチずつに切り分け、それを空中に放り投げて、ランダムにつなぎ合わせるというものでした。それが見事ジョンの検閲をクリアしたわけです。そんなこんなで出来上がったのが、「Being for the Benefit of Mr. Kite!」なのですが、BBCから放送禁止を喰らいます。
なぜ放送禁止になったのか
放送禁止の理由は、馬でした。歌詞に登場する馬の名前「ヘンリー」が引っかかったのです。ポスターにあった馬の名前はZanthus。これをジョンはなぜか「ヘンリー」に変更。それが「ヘロイン(Heroin)」を連想させるとして、アウトだったようです。今思うと、なんだかとっても厳しい措置のような気もしますが、ダメなものはダメだったのでしょう。それにしてもジョンレノン。ポスターの宣伝文句を忠実に歌詞にしたのに、なぜそこだけ変更したのでしょう。意図的なのか、そうでないのか。謎です。
Mother よくわからない理由で放送禁止
ここからはソロ作品に目を向けていきます。ジョンレノンの「Mother」です。1970年12月に発表されたソロデビュー作『Plastic Ono Band』に収録された「Mother」は、ビートルズ解散直後の彼が心の奥底をさらけ出した衝撃作。お母さんのことを歌った曲がなぜか放送禁止です。なぜなのでしょうか?
「Mother」が制作されたのは、ジョンがビートルズから解放されたくらいの時期です。当時、ジョンは、幼少期に経験した深い心の傷を解放し、「真の自分」を取り戻すために、感情解放療法(プライマル・セラピー)を受けていました。そこから得たインスピレーションをもとにこの曲は作られています。ジョンが経験した悲しい過去を赤裸々に表現しているのがこの曲です。
なぜ放送禁止になったのか
ずばり、怖いからです。この曲の親への愛憎をむき出しにした歌詞と、冒頭の鐘の音、断続的に響くシャウトが混ざり合うサウンドは、そのあまりの生々しさゆえに「狂気を煽る」としてアメリカを中心とした一部放送局で放送禁止扱いとなったようです。要するに「聴覚的な刺激が異常」が問題だったわけです。
諸説あり、情報ソースが不安なのですが、事実であるとすると、とんでもない理由ですね。放送禁止の理由が「The よくわからない」です。
Imagine もっとよくわからない理由で放送禁止
最後は、これまたジョンのソロ作品「Imagine」です。人類の最高傑作であり、現地球の主題歌であるこの曲も、放送禁止措置になった経緯を持っています。その普遍的なメッセージと美しいシンプルさを持つ「Imagine」。1971年にリリースされたこの曲は、国境や宗教、所有という概念を超えた平和な世界を目指すジョンの理想が結晶化した作品です。誰でも口ずさめるシンプルなメロディ、比較的平易な英単語で綴られた明快な歌詞で構成されているにも関わらず、既存の価値観を問い直す力強さも持っています。
リリースから50年以上経った今も色あせることなく、むしろ分断の深まる現代社会においてさらに輝きを増しているのが「Imagine」です。そんな名曲がなぜ放送禁止になったのでしょうか?
なぜ放送禁止になったのか
放送禁止の理由は、戦争や社会情勢との関連です。この曲に関しては、その影響力の大きさからか、理由もスケールが違います。「Imagine」が放送自粛の対象となった最初の大きな事例は、1991年の湾岸戦争時でした。当時のBBCは「戦時中に"天国もなければ宗教もない"という歌詞を流すことは不適切である」として、一部のニュース番組での使用を控えました。
2001年の9.11同時多発テロ後には、「Imagine there's no heaven」という一節が犠牲者への配慮に欠けるとして、アメリカの一部ラジオ局が自主規制を実施しました。また、特定の宗教観が強い国々では「宗教的価値観に疑問を投げかける内容」として放送を控える例もありました。
他にも事例は多数です。でも、「なんか違うだろ!」感が半端なくあります。この曲が真に意味するところは、そこじゃない気がします。平和を願う曲が、なんだかんだ理由をつけて、禁止されているように見えてしまいます。
一方でオリンピックの開催などで必ず使われるのもこの曲です。平和の祭典だからでしょうか。それはそれでいいと思うのですが、本当にこの曲が必要とされているのは、やっぱり戦争やテロが横行している時代や地域なんじゃないかと思うのです。
「Imagine」の底力
よくわからない理由っで放送禁止の憂き目を見る「Imagine」ですが、そんな措置をもなんのその、この曲の力を止めることはできないのです。宗教や国家という枠組みを超えて、平和を願う普遍的なメッセージは、時代を越えるのです。
最近では新型コロナによるパンデミックの時です。「Imagine」をリレー形式で歌う動画がSNSに投稿され、話題となりました。賛否はあったようですが、人々がこの曲に「何か」を見出そうとした事実に変わりはありません。
どんな時代でも、どんな国でも、人々が「Imagine」に耳を傾けるのは、それだけこの曲に力があるからです。放送禁止という判断があったにせよ、むしろその判断がいかにこの曲のメッセージが鋭く、そして本質的だったかを証明しているのかもしれません。平和や希望は、決して「当たり障りのないもの」ではなく、時に強く社会の価値観に問いを突きつけるのです。
放送禁止は影響力が大きい証拠
ビートルズとジョン・レノンの楽曲が放送禁止を受けたという事実は、まさに彼らが当時の社会や文化に強烈なインパクトを与えていた証拠です。ここでは、ドラッグ示唆からナンセンス表現、キリストへの言及、「Come Together」のコカ・コーラ呼称、馬の名前、狂気と平和まで、さまざまな切り口で放送禁止になった名曲を紹介しました。どれも音楽としての完成度は高く、その禁止理由には時に首をかしげたくなるような強引さがありましたが、それだけ社会がビートルズの表現を恐れていたとも言えます。
「Being For The Benefit Of Mr. Kite!」の馬の名前なんて明らかにこじつけだと思います。それでも放送禁止を喰らってしまうのは、ビートルズの一言一言に人々が敏感に反応したからだと思います。一番納得いかないのが、「Imagine」ですね。「反戦的」という理由で自粛リストに入ったのが本当であれば「The world is so wrong」です。
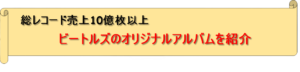 全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
もう少しビートルズを詳しく知りたい方は、歴史を押さえておきましょう。10分で分かるバージョンを用意しております。そして、忘れちゃいけない名曲ぞろいのシングルの歴史もあります。
手っ取り早くビートルズの最高傑作を知りたい方は、ロックの専門誌「ローリングストーン」誌が選出したオールタイムベストアルバムの記事を読んでください。ロックを含むポピュラー音楽史の中で評価の高いアルバムをランキング形式で紹介しています。

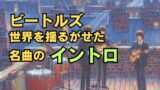
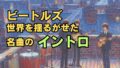

コメント