イントロの一音目が耳を奪い、その後の展開への期待感を一気に高める──これこそビートルズの真骨頂です。令和の今も色褪せない“新しさ”を感じるのは、彼らが曲の冒頭にまで細部の工夫を凝らし、聴き手を音の世界へ引き込む仕掛けを次々に編み出してきたからにほかなりません。イントロは単なる前奏ではなく、「これから始まる物語」の扉。ビートルズはその扉を開ける手法を、様々なパターンで提示し、時代を超えて人々の心をつかみ続けています。
ここでは、ビートルズのイントロを以下の六つのパターンに分類し、それぞれの代表曲を通じてその魅力と革新性を味わっていきます。
- 印象的なフレーズのイントロパターン
―ギターやフィードバック一発で脳裏に刻まれる衝撃的な一音。 - フェードインパターン
―音量を徐々に上げながら静かに引き込む、新感覚の導入部。 - カウントパターン
―「ワン、ツー、スリー、フォー!」という声で、高揚と一体感を呼び覚ます。 - サウンドエフェクトパターン
―劇場のざわめき、飛行機の轟音、鳥の羽ばたき……音楽以外の“風景”を冒頭に再現。 - フランス国歌パターン
―国境を越えるメッセージを担う劇薬のようなイントロ。 - 番外編 イントロなしパターン
―いきなり歌声が響くことで、言葉の力と物語性をダイレクトに伝える究極のシンプルさ。
これらのパターンを聴き比べれば、イントロに込められたビートルズの遊び心と実験精神が浮かび上がります。それぞれの曲が持つ世界観を、イントロの“一瞬”から感じ取り、彼らがいかに時代の先端を走り続けてきたかをぜひ体感してください。次章より、各パターンの代表曲を小見出し付きでたっぷり解説していきます。
ドラム、フィードバック奏法、ギター 一発フレーズパターン
ビートルズのイントロには、ドラムの連打で疾走感を煽り、ギターの“じゃ~ん”一撃で心をわしづかみにし、フィードバックのノイズで耳を引き寄せる──そんなシンプルかつ力強い“瞬間つかみ”のパターンがあります。過剰な装飾を排した一音目が放たれると、「あ、ビートルズだ!」と直感させる強烈な個性が瞬時に炸裂。これにより聴衆は冒頭で心をつかまれ、以後の展開への期待感がぐっと高まります。
1960年代当時、ポップスやロックのイントロはギターやピアノが主流でしたが、彼らはあえてリズムやノイズを前面に押し出し、新たな扉を開きました。今回は、この“究極の一撃イントロ”を象徴する以下の三曲を紹介していきます。
- A Hard Day’s Night
- She Loves You
- I Feel Fine
それでは、早速!
A Hard Day's Night — “じゃ〜ん”の一撃フレーズ
ビートルズのイントロといえば、まず思い浮かぶのが『A Hard Day’s Night』の冒頭の“じゃ〜ん”です。ギターの一発フレーズで始まるこのイントロは、不安定で「どうなるの?」と思わせるような音から始まって、それが一気に安心感のある響きに変わり、聴く人の心を一瞬でつかみます。「ちょっと高めの音を引っかけるように鳴らしてから、一気にメロディに移行する」という流れ。これにより、聴き手は「何が始まるんだ?」という期待感を抱きつつ、一音でビートルズの世界観に引き込まれるのです。
この“じゃ〜ん”は、1964年当時のポップスにはほとんど見られなかった大胆な試みでした。たとえば当時のエルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーは、イントロでリズムやストロークを聴かせるスタイルが主流。そうした伝統的ロックンロールのイントロと比べると、ビートルズは「一発でグッとつかむ」新機軸を打ち出しています。結果として、ラジオやTVで流れた瞬間に「あの曲だ!」と即座に認識されるアイコニックな役割を果たしました。
She Loves You — ドラムだけの疾走感
次にご紹介するのは『She Loves You』のドラムオンリーイントロ。リンゴ・スターが放つシンプルなスネアとハイハットだけで始まるこの一撃は、曲全体の疾走感を象徴しています。「リズムの骨格だけで勢いを出す」技法とでもいいましょうか。ミュートを効かせたスネアのキレと、ハイハットのシャープなカチカチ音が、歌メロ以前からすでに耳を惹きつけます。
当時、イントロをドラムのみで構成するポップス曲はほとんど例がなく、『She Loves You』はまさに“型破り”そのもの。チャック・ベリーやプレスリーの楽曲では、ギターやピアノが先に入るのが普通でしたが、ビートルズはあえて“リズム=躍動”を最前面に押し出すことで、新しい聴きどころを創出。結果として、イントロが鳴った瞬間に「さぁ始まるぞ!」という高揚感が一気に高まります。
I Feel Fine — 世界初のフィードバック奏法
最後は『I Feel Fine』のギター・フィードバックです。イントロで鳴り響くあの独特の「ビーン」という音は、ジョン・レノンがアンプのスピーカーにギターを近づけることで、弦の振動とスピーカーの音が共鳴して生まれたものです。簡単に言うと、「ギターの音がアンプを通して戻ってきて、振動がどんどんふくらんでいく」イメージでしょうか。最初に共鳴音が鳴り、そこからクリーントーンの印象的なギターリフへとスムーズに移行する流れが絶妙。偶然から生まれた効果を、意図的に音源に取り込んだ先駆的な試みでした。
1960年代、フィードバックはマイナス要素とみなされることが多く、ほとんどのミュージシャンが避けていました。しかしビートルズは「ノイズも音楽の一部」として歓迎し、録音の最前線に取り入れます。これ以前にフィードバックをイントロに据えたポップソングは存在せず、後のジミ・ヘンドリックスやローリングストーンズもこの手法を使っていますね。こうしたビートルズの挑戦が、ロックギターの表現力を飛躍的に広げました。
▼ 紹介した楽曲はこのアルバムで聴けます!
ボリュームが徐々に上がってくるフェードインパターン
レコード再生時、曲の音量が小さく始まり、徐々に大きくなる──いわゆる“フェードイン”は、当時のポップスやロックではほとんど見られなかった画期的な手法です。通常、イントロは最初の一打ちや一音で勢いをつかむものですが、ビートルズはむしろ「聴き手の耳をそっと引き寄せる」ことで新たな期待感を生み出しました。フェードインはシンプルに聴こえつつ、スタジオでのミキシング技術や演奏タイミングの正確性が要求されるため、演奏以上に録音時の緻密さが問われる手法でもあります。ここでは、アルバム初期から後期に至るビートルズの代表的なフェードイン三曲──『Eight Days a Week』、『I Want to Tell You』、『Dig It』を紹介します。
Eight Days a Week
『Eight Days a Week』のフェードインは、まさに“前奏のない前奏”とも言えるユニークな始まり方です。冒頭では、高い声のハーモニーだけがかすかに聞こえ始め、少しずつベースやギター、ドラムの音が重なっていき、最終的にバンド全体の演奏が完成します。「はじめはぼんやりと聞こえる音が、だんだんとリズムに乗って形になっていく」という流れです。この静かに始まりだんだん広がっていく感じが、曲全体に漂う“ゆらぎ”のような気持ちよさを予感させてくれます。
当時のR&Bやロックンロールでは、イントロで一気に盛り上げるスタイルが普通でした。つまり、最初から勢いよくスタートするのが王道。でもビートルズは、プロデューサーのジョージ・マーティンとともに、あえて静かなところから始めて、徐々に盛り上げていくという、逆のアプローチを取りました。まるで音の世界が少しずつ目を覚ましていくような感覚です。この演出は当時とても新鮮で、その“じわじわ始まる感じ”に多くの人が驚き、すぐに真似するアーティストが続出しました。
I Want to Tell You
ジョージハリスン作の『I Want to Tell You』では、どこか異国の空気を感じさせるような不思議なギターの音から始まります。まるでシタールのように響くその音は、最初はとても小さく、まるで遠くから聞こえてくるよう。そこに少しずつ他の楽器の音が重なっていき、やがてハッキリとした演奏へと変わっていきます。「ギターが静かに語り始めて、2小節目にはまわりの演奏も加わり、会話が本格的に始まる」というようなイメージです。録音のときには、ギターの音量を少しずつ上げたり、独特な響きが出るような加工をすることで、まるで夢の中で音が近づいてくるような不思議な効果を生み出しています。
『I Want to Tell You』では、ただ音量を上げていくのではなく、音の色合いそのものが変わっていくように工夫されています。この変化によって、最初はどこかぼんやりしていた印象が、徐々に鮮やかになっていく──そんな“音のグラデーション”を感じられるのです。さらに、曲が進むにつれて、普段のポップスではあまり聞かないような響きや展開も登場してきて、「あれ?なんだか不思議だけど心地いいぞ」と感じさせる仕掛けがいっぱい。まさに“聴くドラマ”のようなイントロと言えるでしょう。
Dig It
アルバム『Let It Be』のセッションから生まれた『Dig It』は、フェードインの中でも特に自由で、即興的な魅力にあふれた曲です。メンバーたちが思い思いに音を鳴らしながら、軽いおしゃべりも交えてリズムを作っていく様子が、徐々に音量を上げながらスピーカーから聞こえてきます。そしてそのまま、全員のコーラスに自然につながっていく──そんな“その場の空気”を感じさせる始まり方が、この曲ならではの魅力です。演奏自体はとてもシンプルで、数個のコードを繰り返しているだけですが、聴いている側は「いつみんなが本気で演奏を始めるんだろう?」というワクワク感とともに楽しめます。
前の2曲が「しっかりと作り込まれたフェードイン」だったのに対し、『Dig It』はあえてその場のゆるい演奏をそのまま残し、フェードインで“スタジオにいるような雰囲気”を届けようとしています。それまでのポップスは、演奏や歌がきれいに整っていることが大前提で、そういった“雑音”や“無駄な部分”はカットされるのが普通でした。でもこの曲では、あえてその“雑多さ”をそのまま魅力として見せていて、それが新しかったのです。後に出てくるプログレやジャムバンドと呼ばれる音楽スタイルにも、この感覚はしっかりと影響を与えています。
以上、ビートルズの曲におけるフェードインの使い方を3曲取り上げてご紹介しました。音が少しずつ増えていき、やがて全体がひとつになっていく──そんな流れの中には、ただの演出を超えた“聴かせ方の工夫”があります。次は、カウントから始まるパターンや、効果音を使ったイントロなど、また別のスタイルのイントロについてもご紹介していきます。
ワン、ツー、スリー、フォー!で始まるカウントパターン
イントロでいきなり「ワン、ツー、スリー、フォー!」──このシンプルな合図が放つ力強さは、まさにロックの真骨頂です。ビートルズはデビュー当初から、人間の声だけでリスナーをグッと引き込み、身体の奥底にある高揚感を一気に呼び覚ます技を得意としていました。ギターやドラムが入る前に、まず“声”でテンポと気分を宣言することで、「これから何かすごいことが始まるぞ」という期待を一瞬で最高潮に導く──そんなドラマチックな仕掛けが、このカウントパターンの魅力です。ここからは、ビートルズの代表的な三曲をじっくり見てみましょう。
I Saw Her Standing There
最初の挨拶代わりともいえる「ワン、ツー、スリー、フォー!」のコールから、鮮烈に幕を開ける『I Saw Her Standing There』。ポール・マッカートニーの伸びやかな声が放つ一声は、フレッシュなエネルギーそのものです。合図のあとに流れ込んでくるギターのジャキッとしたストロークは、新鮮な朝日が差し込むように眩しく、聴く者の心を一気につかみます。
このカウントは、まるでステージ上でメンバーが肩を組み、観客に向かって「行くぞ!」と気合を入れる瞬間のよう。ラジオから流れる初期のビートルズは、雑音やチューニングの隙間をものともせず、この“声の合図”で「あ、ビートルズだ」と世界中の耳を総なめにしました。ライブでも一体感を生む最強のオープニングとして、初期ツアーの鉄板ネタになっていたのも納得です。
Taxman
一転してスリリングな空気をまとった『Taxman』のカウントは、鋭く、まるで目の前で何かが始まる寸前の緊張を切り裂くよう。「ワン、ツー、スリー、フォー!」──その声すら楽曲の一部として響き、鳴り止んだ瞬間に噛みつくようなギターリフが飛び出します。
この曲が生まれたのは、世の中への怒りや皮肉を込めた時代。カウントはまるで銃の銃口を構えるように、鋭利な覚悟を伝えます。重たいビートが刻まれる前の“静かな一呼吸”としても機能し、聴き手はその刹那、「今から弾き飛ばされるぞ」という昂揚を全身で味わうのです。エネルギーと皮肉が同居したイントロは、ビートルズらしい“ひねりのあるカウント”と言えるでしょう。
Yer Blues
『Yer Blues』でジョンがつぶやくように放つ「One, two — one, two, three, four」は、まるでステージ袖で仲間と音合わせをしているかのような生々しさがあります。はじめは声だけがポツリと響き、やがて歪んだギターとドラムが寄り添うようにフェードイン。
このカウントは、泥臭いブルースの空気をまといながらも、あえて完璧すぎないタイミングで残されているため、聴き手はまるでライブハウスの暗がりで起こった“瞬間”を目撃したかのような臨場感を味わえます。声の揺らぎが、そのまま曲の哀愁や苦みを象徴し、イントロなしとは一線を画す“完璧な不完全さ”を魅せつける一声です。
ブルースをルーツに持つミュージシャンは、ほとんどの場合ギターリフから曲を始めますが、ビートルズは“声”でブルースの泥臭さを引き出す点がユニーク。しかも、レコーディングでは緻密にタイミングを計測したうえで、このあえてラフに聞こえるカウントを残しており、「完璧な不完全さ」を作品化する手法は、のちのクリエイターたちにも多大な影響を与えました。
カウントパターンは、ただの合図を超え、ビートルズとリスナーをつなぐ“橋渡し”の役割を果たします。人の声が鳴り響く瞬間、身体のリズムと心の高鳴りがシンクロし、「これから始まる物語」を全身で感じさせる──それがビートルズ流のカウントパターンなのです。次章では、劇場のざわめきや飛行機の轟音などを使ったサウンドエフェクトパターンに迫ります。
劇場のざわめき、飛行機の音、鳥の羽ばたき サウンドエフェクトパターン
ビートルズは、1960年代のポップス界で誰よりも早くイントロに“日常の音”を取り入れる手法を編み出しました。楽器が鳴り出す前の環境音を再生し、リスナーをまるで劇場や空港、森の中へと誘う──その描写力はまさに映画のワンシーンを切り取ったかのようです。音楽の始まりを演奏だけで語るのではなく、聴き手の五感に直接訴えかけることで、イントロ段階で曲の世界観を一気に立ち上げる。この斬新なアプローチによって、ビートルズは単なる“歌もの”ではなく、ストーリーテラーとしての地位も確立しました。ここでは代表的な三曲を取り上げ、それぞれのサウンドエフェクトがどのように曲の物語や雰囲気を彩っているかを紹介します。
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
扉を開けると、そこは熱気とざわめきに包まれたライブハウス。『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の冒頭では、客席のざわめきやカサカサという音がステレオで広がり、観客の興奮と期待感がリアルに伝わってきます。そのまま劇場の暗がりに吸い込まれるようにして、突然ホーンセクションのファンファーレが「パン!」と鳴り響く。この瞬間、聴き手はまるでステージのど真ん中に立っているかのような高揚を覚えます。効果音が切り替わるタイミングも絶妙で、静寂から賑わい、賑わいから華やかな演奏へと自然に移行。従来のレコード再生では得難かった“物語の始まり”を直感的に体感させる演出は、以後多くのアーティストがライブ感を再現する手法として模倣するほどの革新性を誇りました。
Back in the U.S.S.R.
ジェット機のエンジン音──それがゆっくりと頭上を通り過ぎるように左右のスピーカーを行き来しながらフェードインする『Back in the U.S.S.R.』のイントロは、「旅の興奮」をありありと描き出します。疾走感あふれる轟音が近づくにつれ、心臓の鼓動が速くなるような高揚感が胸を打ちます。飛行機が着陸態勢に入るかのごとく轟音が一瞬静まる瞬間、その隙を突くように歪んだギターリフが一気に吐き出され、まるで機体からドアが開いて大地に降り立った瞬間の解放感を再現。音の動きが視覚的にもイメージできるほど明快で、ヘッドフォンで聴けばまるで機内で耳に届く振動やざわめきまでも感じ取れるほどの臨場感を生み出しています。この“飛行機+ギター”の掛け合わせが、旅情と興奮を同時に喚起する斬新さは、今日の音楽制作でもなお色褪せない名手法です。
Across the Universe(バード・バージョン)
静かな森の奥で小鳥たちがさえずり、羽ばたきがそよ風に乗って聞こえてくる──『Across the Universe』バード・バージョンのイントロは、そんな風景を切り取ったかのように始まります。自然のリズムが奏でる優しい高域がゆらゆらと漂い、その場に身を置いて深呼吸する感覚を誘発。やがて穏やかなギターとつながると、まるで森の奥から歌声がこだまするようにメロディが流れ出し、聴き手は一体化したかのように心を澄ませます。このイントロは単なる“飾り”ではなく、フィールドレコーディングで捉えた鳥の声をループさせ、楽曲のテーマである「宇宙にこだまする想い」というコンセプトと完璧に重ね合わせています。自然音を音楽の一部として、しかも冒頭からドラマチックに機能させた試みは、現代のアンビエントやニューエイジにも通じる先駆的な表現技法と言えるでしょう。
以上、劇場のざわめき、飛行機の轟音、鳥の羽ばたきを取り入れたサウンドエフェクトパターンを感覚的に解説しました。いずれも単なる効果音ではなく、曲の扉を開く“物語のプロローグ”として、イントロの役割そのものを再定義したビートルズの革新性を改めて感じていただければ幸いです。次は、さらに多彩なビートルズのイントロ技法をご紹介します。
フランス国歌パターン――ラ・マルセイエーズをイントロに据える大博打
フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」パターンです。1曲しかないので、パターンとはいえないのですが、まあ、いいのです。言わずと知れた『All You Need Is Love』です。自国・英国の国歌でも、リバプールの民謡でもなく、あえてフランスの国歌を選ぶ──この大胆すぎる仕掛けは、1967年当時のポップシーンにおいて前代未聞の“政治的パフォーマンス”とも言えます。イントロから漂うパリの風景は、曲がもつ「愛は国境を越える」というメッセージと見事にシンクロし、一音で世界中のリスナーの心をつかみました。
当時、ポップソングに国家の公式楽曲を取り入れる試みは皆無に等しく、ましてやビートルズほどの人気グループが国歌をイントロに流すのはまさに大博打。しかし、ビートルズはきわめて狡猾にこの手法を使いました。フェードインする国歌のフレーズはごく短くカットされ、すぐにオリジナルのストリングスとホーンで彩られたモダンな楽曲に切り替わるため、「おや?」と思った刹那に心地よいメロディへと誘われる仕掛けになっています。このメリハリが、イントロでのインパクトを最大化し、本編での「愛の普遍性」を力強く感じさせる役割を果たしているのです。
All You Need Is Love
1967年6月25日に放送された、世界初のテレビ衛星中継番組『OUR WORLD』。この歴史的な企画で、ビートルズはイギリス代表として出演し、新曲『All You Need Is Love』を全世界に向けて披露しました。番組では、日本、アメリカ、ヨーロッパ各国などが短いパフォーマンスを行う中、ビートルズは曲の冒頭で、短く編集した「ラ・マルセイエーズ(フランス国歌)」をフェードインさせ、そのままオリジナル曲へと自然につなげています。
このフランス国歌の使用には、いくつかの意味合いがあったと考えられます。フランスは当時、文化の中心地として世界的な存在感を放っていたため、あえてそこに敬意を示しつつ、イギリス発のポップカルチャー、つまりビートルズが新たな時代の主役であることをさりげなくアピールする意図もあったかもしれません。
とはいえ、ビートルズは国歌を政治的な主張として使ったわけではありません。あくまでイントロの短いワンフレーズにとどめ、「国も文化も違うけれど、みんな愛でつながれる」という楽曲のテーマを、自然に感じさせるための演出であるような気もします。
以降、サッカーの試合などで「ラ・マルセイエーズ」を耳にするたびに、ビートルズを思い出すリスナーが続出したと伝えられています。このエピソードは、イントロのわずかな演出でさえ世界中に影響を与える、ビートルズの存在感を象徴する出来事と言えるでしょう。
以上、『All You Need Is Love』のフランス国歌イントロに込められた工夫についてご紹介しました。国家の一節をさりげなく取り入れることで、「愛は国境を越える」というメッセージをより強く伝える──イントロから本編まで、聴き手を一瞬で引き込む手腕は、やはりビートルズならではです。
番外編 イントロなしパターン
イントロがない――つまり「いきなり歌声が飛び込んでくる」パターンは、ビートルズのもう一つのお家芸です。楽器の合図や効果音を待つことなく、冒頭の一言でリスナーをぐっと引っ張り込み、曲の世界へとダイレクトに没入させる。まるで舞台の幕がいきなり上がる瞬間、その一声で物語が始まるような衝撃があります。ここでは、アップテンポからミドルテンポまで幅広く使われた「イントロなしパターン」の代表曲六選をご紹介します。
All My Loving
「Close your eyes and I’ll kiss you…」という柔らかい囁きで幕を開ける『All My Loving』。ありふれたギターやドラムのスタートをすっぱり切り捨て、いきなりポールの甘いボーカルだけが部屋を満たします。その声は、手紙をしたためているような優しさと、ほんのり切なさが同居。リスナーは一瞬で「これは大切な人へのラブレターだ」と感じ、心の中に温かなシーンを思い浮かべながら聴き進めることになります。イントロなしで歌詞世界に直結するからこそ、曲の中心にある“想い”がクリアに伝わるのです。
No Reply
『No Reply』では、ジョンの少し低めで切ない声が、静かに空気を満たすように始まります。冒頭からギターのアルペジオが淡く寄り添うものの、目立った前奏はなく、いきなり歌がスタートする構成です。出だしの一行「This happened once before, when I came to your door, no reply」は、まるで短編小説の冒頭のようですね。聴く者は瞬時に、恋人に拒絶された哀しい情景を思い描き、物語の続きを知りたくてたまらなくなります。イントロを省いたことで、歌詞のドラマ性とジョンの感情表現がよりダイレクトに伝わり、曲全体の印象を深く刻み込む仕掛けとなっているのです。
Help!
タイトル通り、鋭く「Help!」と叫ぶ声でスタートする『Help!』は、その緊急感と切迫感に、思わずリスナーの心をつかみます。冒頭、ジョンのリードボーカルに、ポールとジョージのコーラスが重なり、一瞬で緊張感が高まる構成。ギターやドラムは控えめに支え、まずは“叫び”そのものが前面に出るアレンジとなっています。イントロを待たず、いきなり感情が爆発することで、聴き手は「何が起きたのか?」と強く引き込まれ、曲の本編に向けて自然と心拍数を高めていく仕掛けになっているのです。
We Can Work It Out
『We Can Work It Out』も同様に、最初の一声「Try to see it my way」でスタート。頭からエンジン全開というよりは、暖かな日差しの中で二人が会話を始めるような優しいタッチです。歌い出しの言葉がそのまま提案や対話の扉となり、リスナーは曲という“会話のテーブル”に自然と招かれます。イントロなしの心地よさは、楽器が入る前の静寂を感じさせ、歌詞のメッセージ性を際立たせる効果を持ちます。
Girl
『Girl』は、しっとりとしたミドルテンポにもかかわらず、ギターすら鳴らさずに冒頭の「Is there anybody going to listen to my story…」で深い物語を開きます。その一言は、映画のナレーションのように淡々とシリアスな空気を漂わせ、リスナーは秘密を打ち明けられるような特別感を抱くでしょう。イントロなしだからこそ、歌詞のひとことひとことが絵画のタッチのように鮮やかに浮かび上がります。
Hey Jude
『Hey Jude』は、長大なエンディングで知られますが、序盤もイントロなしのパターン。ポールが優しく語りかけるように「Hey Jude, don’t make it bad…」と始めるその声は、慰めと励ましを帯び、聴き手の心にそっと寄り添います。まるで親しい友人にかける言葉のように、イントロなしの開口一番が曲全体の包容力を決定づける役割を果たします。徐々に楽器が重なり合い、最後のコーラスへとつながる流れは、歌い出しの声がもたらした“安心感”に支えられているからこそ生まれるのです。
イントロなしパターンは、楽器の“装飾”を一切排し、歌の持つドラマ性や情感をダイレクトに伝える究極のシンプルさを体現しています。ビートルズはこの手法を自在に操り、アップテンポのロックからミドルテンポの叙情曲まで幅広く応用しました。その結果、「一言目で心をつかむ」強烈なインパクトを生み出し、リスナーを物語のど真ん中へと誘う技法として、後のアーティストにも多大な影響を与えています。
聞くと忘れられないインパクトのあるイントロで世界をつかむ
今回は、イントロのパターンあれこれをご紹介してきました。どれもこれもインパクトが大きいものばかりです。イントロ一つをとっても様々な工夫がなされており、聞けば一発で「あ、ビートルズだ!」と思わせるすごさを持っています。聞く者の心を一瞬でつかみ、そこから放さない凄みがあります。
制作の過程で、試行錯誤は数多くやったのでしょう。『アンソロジー1』に収録されているEight Days a Weekを聞くと、そのこだわりがよくわかります(こっちのバージョンも良い!)。すでに超有名であったにもかかわらず、世界中の人々に自分たちの歌を届けようとあちこちに仕掛けをほどこしているのです。頭があがりません。ビートルズは常に進化していたのだと思います。
▼ 紹介した楽曲はこのアルバムに収録されています(すべてじゃないです)
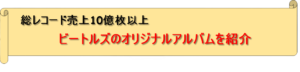 全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
もう少しビートルズを詳しく知りたい方は、歴史を押さえておきましょう。10分で分かるバージョンを用意しております。そして、忘れちゃいけない名曲ぞろいのシングルの歴史もあります。
手っ取り早くビートルズの最高傑作を知りたい方は、ロックの専門誌「ローリングストーン」誌が選出したオールタイムベストアルバムの記事を読んでください。ロックを含むポピュラー音楽史の中で評価の高いアルバムをランキング形式で紹介しています。





コメント