もし、ビートルズがもう一枚アルバムを作っていたら…。
1969年、『Abbey Road』を完成させたビートルズは、すでにバンドとしての限界に直面していました。それぞれが異なる道を歩み始め、音楽の方向性も、人生の選択も、少しずつズレ始めていたのです。しかし、完全に決裂する前のある日、4人は次のアルバムについて話し合っていました。その記録が音声として残されていたことが、近年明らかになったのです。
そこには、かつてのような和気あいあいとした雰囲気はもうありませんでした。それでも彼らは、新しいアルバムの構想を語り合い、それぞれの楽曲を持ち寄ろうとしていました。もし、この話し合いが実を結んでいたら、ビートルズ最後のアルバムはどんな形になっていたのでしょうか?
ここではジョンレノンの4曲とポールマッカートニーの4曲、ジョージハリスンの4曲に、リンゴの2曲を加えた「幻のアルバム」を考えてみました(収録曲の選定は別の記事を参照してください)。もし、このアルバムが実現していたら、音楽史はどう変わっていたでしょうか? ここでは、そんな「もしも」のアルバムを考えたいと思います。異論反論あると思いますが、優しい感じでお願いします。では、さっそく!
1. Cold Turkey
アルバムのオープニング飾るのは「Cold Turkey」です。その強烈なインパクトと生々しいエネルギーはアルバムの幕開けにピッタリ。ジョンのソロ作品の中でも特に攻撃的なサウンドを持ち、ビートルズ後期の実験的な音作りを受け継ぐこの曲を冒頭に配置することで、聴き手は一気に引き込まれ、アルバム全体の空気が張り詰めたものになること間違いなしです。
「Cold Turkey」は、ジョンが1969年に発表したソロシングルです。危険な薬物の禁断症状を表現しており、そのタイトルは薬物を断つ際の激しい症状を指すスラングから取られています。ジョンはこの曲で、薬物依存の苦しみを赤裸々に描きながら、同時に社会への強いメッセージも込めました。
この曲は当初ビートルズでの録音が検討されました。しかし、メンバーの賛同を得られず、ジョンはプラスティック・オノ・バンドとしてレコーディングを敢行。エリック・クラプトンのギター、クラウス・フォアマンのベース、アラン・ホワイトのドラムが加わり、シンプルながらも圧倒的な迫力を持つアレンジが施されました。ビートルズ版が実現していたらどうなっていたでしょうか。
「Cold Turkey」の最大の聞きどころは、その緊張感あふれるサウンドです。重厚なドラムとベースのリズムの上で、ジョンのギターが鋭いリフを繰り返します。禁断症状の苦しみを音で表現しているかのようなそのリフは、聴く者を圧倒します。そして、ジョンのボーカルはまさに圧巻です。時にうめき、時に叫びながら、薬物依存の恐怖と苦しみをリアルに表現しています。特に、終盤で繰り返される叫び声は、耐えがたい苦しみの頂点を象徴するかのようです。
曲のラストに向かってギターのフィードバックノイズが増幅し、まるでジョンの内面の混乱や絶望が音として爆発するような効果を生み出します。ビートルズ時代の「Revolution」や「Yer Blues」を彷彿とさせながらも、より過激でストレートな表現が際立っています。この強烈なメッセージとサウンドは、アルバムの1曲目としてふさわしいものです。
2. Another Day
アルバムの2曲目に「Another Day」を選んだのは、「Cold Turkey」の激しさの後に一息つける流れを作るためです。ジョンの攻撃的なロックナンバーの後に、ポールの優しく切ないバラードを配置することで、アルバム全体に緩急をつけ、感情のコントラストを生み出します。
「Another Day」は、ポールが1971年に発表した最初のソロヒット曲です。都会で孤独に生きる女性の姿を描いた歌詞と、哀愁漂うメロディが特徴的で、ポールのソングライティングの巧みさが際立っています。実はこの曲はビートルズ時代に原型ができており、1969年頃には断片が作られていましたが、正式なビートルズの楽曲とはなりませんでした。なんてこった!
曲は、シンプルですが、ポールの温かいボーカルが聴き手を物語の世界へ引き込みます。「Every day she takes a morning bath...」という冒頭の歌詞は、日常の繰り返しを淡々と描きながらも、その裏にある孤独を感じさせます。曲の後半で繰り返される「So sad, so sad...」のフレーズは、主人公の寂しさを強調し、ポールの情感豊かな歌声がその切なさを際立たせています。
アレンジにはギターやストリングスが効果的に使われ、柔らかく包み込むようなサウンドを作り出しています。派手さはないものの、細部にわたる繊細な表現が、この曲の魅力を際立たせています。
「Another Day」は、ポールのソロキャリアを象徴する楽曲の一つであり、その普遍的なテーマと美しいメロディが多くのリスナーに響きます。「Cold Turkey」の激しい衝撃の後にこの曲が続くことで、アルバム全体の流れに心地よいバランスが生まれ、聴き手を次の展開へと導いていきます。
3. Gimme Some Truth
「Gimme Some Truth」は、アルバムの3曲目にふさわしい力強いメッセージとエネルギッシュなサウンドを持った曲です。1曲目「Cold Turkey」の強烈なロックナンバーから、2曲目「Another Day」の穏やかなバラードを経て、再びジョンの声がアルバムに緊張感と怒りをもたらします。この曲は、ジョンが当時の政治や社会に対する不満をストレートにぶつけた作品で、その率直なメッセージが心を揺さぶってきます。ポールの穏やかな曲の後にジョンの怒りを込めた声を響かせたいのです。
「Gimme Some Truth」は、ジョンが1971年にリリースしたアルバム『Imagine』に収録された曲です。ベトナム戦争や政治的な偽善に対するジョンの怒りをそのまま音にしたような作品で、彼の政治的活動が最も活発だった時期に生まれました。ジョンは、「Gimme Some Truth(真実をくれ)」というシンプルながらも力強いフレーズに感情を込めています。ビートルズ時代から温めていたアイデアを再び取り上げ、ソロ作品として完成させたと言われています。
この曲の最大の魅力は、そのストレートなメッセージとエネルギッシュなサウンドです。ジョンの鋭いギターリフと、フィル・スペクターによる重厚なサウンドが特徴的で、聴く者に強いインパクトを与えます。ジョンのボーカルは、怒りと切迫感に満ちており、特に「I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites」というフレーズでは、彼の感情が爆発する瞬間を感じ取ることができます。この曲のメッセージ性とサウンドの力強さが、アルバム全体に緊張感を与えてくれます。
4. It Don’t Come Easy
4曲目はリンゴの「It Don't Come Easy」です。『Abbey Road』の次回作に収録される可能性は低そうですが、そこはまあ、いいじゃないですか、ということで強引に選曲しました。この曲をここに配置することで、これまでの流れに新たな風を吹き込みたかったのです。ジョンの「Gimme Some Truth」が投げかけた緊張感と怒りを、リンゴの明るく温かいサウンドが優しく包み込み、バランスをとりたかったのです。
この曲は、リンゴが1971年にリリースしたソロシングルで、彼のソロキャリアを代表するヒット曲として知られています。この曲は、ジョージがプロデュースを手掛け、リンゴ自身が作詞作曲を担当しました。曲のテーマは、人生の困難や挑戦を乗り越えるための忍耐と希望を歌っており、リンゴの温かい人柄がそのまま音になったような作品です。ビートルズ解散後、リンゴはソロアーティストとしての新たな一歩を踏み出し、この曲を通じて彼自身のメッセージを世界に届けました。
「It Don’t Come Easy」の最大の魅力は、そのキャッチーなメロディとリンゴの温かいボーカルではないでしょうか。歌詞は、人生の困難に直面した時に必要な忍耐と希望を歌っており、多くの人々が共感できる普遍的なテーマを持っています。曲のアレンジも見逃せません。リンゴのドラムに加え、ジョージによるギターの軽やかな音色が曲に彩りを加え、聴き手を優しく包み込むようなサウンドを作り出しています。
「It Don’t Come Easy」は、リンゴがソロアーティストとしての新たな一歩を踏み出した記念碑的な曲です。そのメッセージとサウンドは、アルバムの4曲目としてふさわしいだけでなく、聴き手に強い印象を残すこと間違いありません。
5. All Things Must Pass
でました!ジョージの大名曲「All Things Must Pass」です。この曲は、アルバムの中盤に差し掛かり、これまでの流れに哲学的で内省的な色彩を加える役割もっています。ジョンの「Gimme Some Truth」やリンゴの「It Don’t Come Easy」がそれぞれの形でメッセージを投げかけた後、ジョージのこの曲は、それらを受け止め、静かに思索へと導きます。アルバムの流れとして、これまでのエネルギッシュな曲調から一転、ジョージの穏やかながらも深遠な歌声が、聴き手に内省の時間を提供するのが狙いです。この曲は、ジョージのソロキャリアの中でも特に重要な楽曲の一つで、その詩的な歌詞と壮大なサウンドが、アルバム全体に重厚感をもたらしてくれるはず!
「All Things Must Pass」は、ジョージが1970年にリリースした同名アルバムのタイトルトラックであり、彼のソロキャリアを代表する作品の一つです。この曲は、ビートルズ時代に原型が作られており、ジョージがバンド内でなかなか自分の曲を発表する機会が少なかったことへの思いも込められているようです。曲のテーマは、人生の儚さや変化の必然性を歌っており、仏教的な思想やジョージ自身のスピリチュアルな探求が反映されています。
最大の魅力は、その詩的な歌詞とジョージの情感たっぷりのボーカルです。曲は、静かなギターのアルペジオで始まり、ジョージの優しい声が聴き手を物語の世界に引き込みます。それから、ジョージのギターもいいですね。フィル・スペクターも重厚なストリングスやコーラスが曲に厚みを加え、聴き手を優しく包み込むようなサウンドを作り出しています。もしビートルズバージョンがあったら、一体どんなサウンドになっていたのでしょうか。
6. Junk
「Junk」は、アルバムの中盤でこれまでの流れに新たな風を吹き込む役割を果たします。ジョージの「All Things Must Pass」が投げかけた内省的な雰囲気を、ポールの優しくも切ないバラードが優しく包み込みこんでくれます。ジョージのスピリチュアルからのポールの優しい楽曲です。安らぎとともに、アルバムへの新たな興味が湧いてきますね。
「Junk」はポールが1970年4月に発表した初のソロアルバム『McCartney』に収録された曲です。もともとビートルズの「ホワイト・アルバム」や「アビーロード」セッション時に作られたものの、バンドのアルバムには採用されず、ポールのソロ作品となりました。アルバム内では楽器演奏版「Singalong Junk」も収録されています。
「Junk」はメランコリックな雰囲気と、シンプルながら印象的なメロディが特徴です。ポールが自宅スタジオで全ての楽器を演奏し録音したこの曲は、アコースティックギターから始まり、ピアノやパーカッション、メロトロンのフルート音などの控えめな楽器編成で構成されています。歌詞は捨てられた物や忘れられた記憶についての断片的なイメージが描かれており、物の価値や消費についての考察を含んでいます。日常的な物のリストが過ぎ去った記憶を表現し、静かなノスタルジーを感じさせます。
この曲が作られた背景には、ビートルズ解散があります。ポールはバンドから離れ、妻リンダとともにスコットランドの農場で過ごしていた時期に、より個人的な音楽スタイルを模索していました。「Junk」はそうした時期に生まれた作品です。録音方法も注目に値します。ビートルズ時代の洗練された録音とは異なり、4トラックのテープレコーダーを使った自宅録音で、素朴な音質と演奏が残されています。この「手作り感」が曲の雰囲気に合っています。
7. Give Peace a Chance
「Give Peace a Chance」は、アルバムのA面を締めくくるにふさわしい、力強いメッセージ性とシンプルながらも印象的なサウンドを持った曲です。これまでのジョン楽曲、「Cold Turkey」や「Gimme Some Truth」がそれぞれの形でメッセージを投げかけてきた後、この曲はそれらを集約するかのように、平和への願いをストレートに訴えます。やはり最終的には「平和」なのです。
「Give Peace a Chance」はジョンが1969年に発表したソロシングルで、彼のソロキャリアを代表する作品です。この曲はジョンとオノ・ヨーコがモントリオールのクイーン・エリザベス・ホテルでベッド・インを行っている最中に録音され、その場に居合わせた友人や著名人たちがコーラスとして参加しています。でも、作詞作曲のクレジットはレノンマッカートニーなのです。
曲の特徴はシンプルさにあります。繰り返される「All we are saying is give peace a chance」というフレーズは、単調なリズムとコード進行で構成されており、誰でもいつでも口ずさめるようになっています。この単純さこそが、この曲の最大の魅力。平和を願う楽曲であることを強烈に印象付けています。
アルバムの構成上では、ポールの「Junk」の穏やかな雰囲気から一転、ジョンの力強いメッセージドングです。前半の「Cold Turkey」や「Gimme Some Truth」が投げかけたメッセージを集約するような位置づけにもなっています。
さて、続いてはB面です(レコード想定)。
8. Photograph
B面の1発目はリンゴの「Photograph」です。この曲を『Abbey Road』の次回作に持ってくるのは、いくら想像上のことであっても無理があるんじゃないかと思いますが、まあ、いいのです。ビートルズはいつだって想像を超えてくるので、このくらいのぶっ飛びはいいのです。
この曲は、リンゴが1973年に発表したシングルで、彼のソロキャリアを代表するヒット曲のです。なんと、全米チャートで1位を獲得しています!この成功はビートルズ解散後のリンゴの音楽キャリアにおける重要な転換点となったのではないでしょうか。
アルバムの構成としては、この曲はB面の始まりに位置し、A面最後のジョンの「Give Peace a Chance」の力強いメッセージから一転、より個人的で情感豊かな雰囲気へと誘うのが狙いです。感情豊かなメロディとリンゴの歌声を聴いて癒されたいのです。
印象的なピアノのイントロから始まるこの曲は、次第に広がりを見せる楽曲構成が特徴です。失った愛や過去の思い出を写真を通して振り返るという内容は、ビートルズのことかな、なんて想像がめぐります。「Every time I see your face, It reminds me of the places we used to go」なんてフレーズは、まさにそうじゃないでしょうか。
注目すべきは、この曲、ジョージとの共作であること。ジョージはプロデュースも手がけています。二人のビートルズメンバーによる協力は、バンド解散後も続いた彼らの友情を象徴するものですね。
9. Hear Me Lord
B面2曲目はジョージの「Hear Me Lord」を持ってきました。この曲は1970年に発表したアルバム『All Things Must Pass』に収録された曲で、彼のソロキャリアにおける重要な作品の一つです。ビートルズ時代から温めていた楽曲で、スピリチュアルなテーマであり、ジョージの内面的な探求を色濃く反映しています。
アルバムの構成としては、リンゴの「Photograph」が投げかけたノスタルジックなメッセージを受け止め、より深い内省的な世界へと聴き手を導きます。この曲の静謐な雰囲気と祈りのような歌詞は、アルバム全体に不思議な雰囲気をもたらすこと間違いなしです。
楽曲は静かなギターのアルペジオから始まり、次第にフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」絡みの壮大なアレンジへと発展していきます。重厚なストリングスやコーラスが加わり、雰囲気はより「祈り」の感じが増幅されていますね。特に「Hear me Lord, won't you hear me Lord」という繰り返されるフレーズは、まさしく神との対話です。
ジョージのボーカルにも注目です。彼の声には人間としての弱さや葛藤が滲み出ており、心に直接訴えかけるような親密さを感じられます。この曲は、ビートルズ解散直後のジョージが自身の音楽的・精神的アイデンティティを確立していく上で重要な作品となりました。彼のインドへの傾倒とスピリチュアルなメッセージは、後の彼の作品にも一貫して流れるテーマとなっていきます。
10. Child of Nature
続いては「Child of Nature」です。この曲はジョンが作曲した曲で、その起源はビートルズのインド滞在時に遡ります。1968年、ジョンがリシケシでマハリシ・マヘシュ・ヨギの瞑想講座に参加していた際に着想を得たこの曲は、後に大きく姿を変えることになります。ジョンの代表曲とも言える「Jealous Guy」です。
歌詞は完全に書き換えられたものの、その特徴的なメロディラインはビートルズ時代の時のまま。当初の「Child of Nature」の歌詞は自然との一体感や単純な生き方への憧れを描いており、インドでの経験が直接反映されていました。ジョージの深ーいスピリチュアリティ楽曲の後に、自然を感じるこの楽曲を配置してみました。ジョンの柔らかな歌声と優しいギターの響きが、前曲の瞑想的な雰囲気から日常へと戻してくれます。
曲の録音には、ジョンのアコースティックギターを中心に、軽やかなピアノやドラムが加わり、シンプルではありますが、心地よい音の広がりを生み出しています。そして、ジョンの透き通ったようなあの声はなんと表現したらいいのでしょう。感動的な歌声です。
それにしても、なぜこの曲は、『ホワイト・アルバム』に収録されなかったのでしょうか。あのアルバムあってもぜんぜん違和感がないです。『ゲットバック』セッションでも取り上げられたみたいですが、そこでも採用されずでした。謎です。
余談ですが、歌詞の変遷も面白いのです。「Child of Nature」の歌詞の冒頭は「On the road to Rishikesh」だったのに対して、『ゲットバック』セッションでは「On the road to Marrakesh」と変化しています。インドの聖地からなぜかモロッコへと変化しています。最終的には「Jealous Guy」になるわけですが、間にいったい何があったのでしょうか。
11. Isn’t It a Pity
「Isn't It a Pity」はジョージが1970年に発表したソロデビューアルバム『All Things Must Pass』に収録された曲です。この曲、実はビートルズ時代から存在していたのだとか。でも、ビートルズのアルバムには採用されず、ジョージの個人作品として花開くことになりました。
曲の特徴は、徐々に積み重ねられる壮大なサウンドですね。最初は静かなギターとジョージの優しい歌声で始まり、次第に重厚な楽器編成へと発展していきます。フィルスペクターの仕業です。後半では繰り返される「Isn't it a pity, isn't it a shame」というフレーズが、クセになりますね。個人的に、ちょっと「Hey Jude」のエンディングに似ていると思っているのですが、いかがでしょうか?
歌詞は人間関係の難しさや愛の喪失を描いています。普遍的なテーマではあるのですが、やっぱりどうしてもビートルズ解散前後の人間関係と解釈してしまいます。でも、ジョージにとっては、より広い視点から人間の条件について歌っているのかもしれません。
「Isn't It a Pity」は、ビートルズのメンバーだった時には十分に発揮できなかったジョージの作曲力と表現力を示す重要な作品です。初めて聴く人にとっては、その7分を超える長さに驚くかもしれません(このあたりも「Hey Jude」に似ている!)。最後まで聴き終えると、満足感たっぷりです。
12. Let It Down
「Let It Down」もまた、ジョージのソロアルバム『All Things Must Pass』に収録された楽曲です。もともとはビートルズ時代に書かれた曲で、1969年の『Get Back』セッションでも演奏されましたが、当時は正式に採用されませんでした。その後、ソロアルバム制作の際に改めて取り上げられ、フィル・スペクターのプロデュースによって壮大なサウンドに仕上げられています。
この曲は、静かなギターのアルペジオで始まり、次第に音が重なり、一気にダイナミックなサウンドへと展開していきます。分厚いドラムとギターのリフが印象的で、サビでは一気に高揚感が生まれます。ジョージのボーカルも、穏やかさと力強さを行き来しながら、曲の流れに合わせて感情を高めていきます。
歌詞のテーマは、内面の葛藤や精神的な探求でしょうか。恋愛や人間関係に対する思いが込められているとも解釈できますが、それだけでなく、より大きな視点での精神的な解放を訴えているとも考えられます。特に「Let it down, let it down, let it all down」という繰り返しのフレーズは印象的ですね。抑えていた感情や思いを解き放つような強いメッセージを感じさせます。
アルバムの流れとしては、「Isn’t It a Pity」の後に続けてのジョージの楽曲です。静かな雰囲気の全曲から一転して、エネルギッシュなサウンドが展開される流れです。これにより、アルバム全体が単調にならないようにしています。加えて、ここでジョージの存在感を一気に出していきます。
13. Every Night
いよいよアルバムも終盤です。13曲目はポールの「Every Night」です。この曲は、1970年に発表されたアルバム『McCartney』に収録された楽曲です。ビートルズ解散直後の混乱の中で生まれたこの曲は、ポールが精神的に不安定だった時期を反映しながらも、新たな人生への希望を感じさせる内容となっています。辛い時期でもポジティブさを垣間見せてくれるのがポールです。
この曲は、1969年にギリシャでの休暇中に書かれ、最初の2行は同年のビートルズのゲット・バック・セッションの時点で存在していたようです。ポールはこの時期、音楽活動への意欲を失い、家族と過ごすことに救いを求めていました。「毎晩、ただ何もせずに過ごしたい」という歌詞には、その当時の気持ちが素直に表れているのかもしれません。
曲は、アコースティックギターの優しい音色で始まります。ギターは一つひとつの音を丁寧に奏でるように弾かれ、シンプルながらも耳に残るメロディが印象的。その背後には、控えめなベースとドラムが加わり、ポールの歌声をそっと支えています。ポールのボーカルは、落ち着いた雰囲気の中にも、時折感情の揺れが感じられ、歌詞の内容とも相まって、心に響いてきやがります。シンプルな構成だからこそ、ポールの思いがストレートに伝わってくる仕上がりになっています。もしビートルズバージョンがあったら、どうなっていたでしょうね。
「Every Night」は、ポールがシンプルな音楽の魅力を再発見したことを示す楽曲でもあります。派手な演出はないものの、素直な歌詞とメロディが持つ力によって、心に深く残る作品となっています。
14. The Back Seat of My Car
アルバムのラストを飾るのはこの曲です。「The Back Seat of My Car」です。この曲は、ポールのアルバム『Ram』に収録された作品で、やはりアルバムの最後を飾っています。アルバム全体の流れを総括するかのような、ダイナミックな展開と情熱的な歌声の融合は、もう圧巻です。ポールのソロキャリアにおいても象徴的な作品であり、その音楽的な野心と表現力の豊かさが際立つ一曲です。
この曲は、ポールがビートルズ解散後の混乱と再出発の狭間で生み出した作品であり、若者の恋愛と自由をテーマにしながら、同時に彼自身の音楽への情熱と決意を込めたものでもあります。この曲の原型はビートルズ時代にすでに存在していたのだとか。ただ、正式なレコーディングには至っていません。なんてこった!です。
この曲の魅力は、緻密に計算された構成にあります。静かで穏やかなイントロから始まり、少しずつ盛り上がりながら、やがて圧倒的なクライマックスへと突き進む展開。「Hey Jude」のように観客と一体になるような壮大さとは異なり、よりドラマチックで劇的な迫力を持つのがこの曲の魅力です。特に、終盤で「We believe that we can’t be wrong」というフレーズが繰り返される部分は、楽曲のクライマックスとしてかなりのインパクトです。この曲の壮大なフィナーレは、ビートルズ時代の『A Day in the Life』にも通じるドラマチックな展開を持ち、ポールの作曲家としてのスキルと演出力の高さを存分に示しているのではないでしょうか。
アルバムの締めくくりとして、「The Back Seat of My Car」はピッタリだと思うのですが、いかがでしょうか。この曲を聴き、アルバム全体の余韻に浸ることで、ビートルズの音楽世界の奥深さを改めて感じることができるはずです。
まとめ 『Abbey Road』の次回作も魅力的!
もし『Abbey Road』の後にもう一枚アルバムが生まれていたら…。音楽史の大きな「もしも」です。近年見つかった音声記録の内容が真実だとしたら、ビートルズは次回作の可能性は十分にあったのかもしれません。今回、その可能性にもとづいて『幻のアルバム』を考えてみました。いかがでしたでしょうか?アルバムのハイライトはどこでしょうね。「All Things Must Pass」かな。
各メンバーの才能が最高潮に達していた時期だけに、幻のアルバムがあったなら、間違いなく『Abbey Road』に匹敵する魅力を持つものになっていたでしょう。永遠に幻となった「最後の傑作」の可能性は、いまなお、ファンの心をくすぐってきます。
以上、「もしビートルズが『Abbey Road』の次回作を作っていたら 幻のアルバムの14曲!」でした。おしまい!
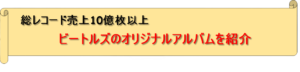 全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
全オリジナルアルバムの聞きどころを紹介。詳しいアルバムガイドです。購入に迷っている方は読んでください。 クリックして詳しく読む
もう少しビートルズを詳しく知りたい方は、歴史を押さえておきましょう。10分で分かるバージョンを用意しております。そして、忘れちゃいけない名曲ぞろいのシングルの歴史もあります。
手っ取り早くビートルズの最高傑作を知りたい方は、ロックの専門誌「ローリングストーン」誌が選出したオールタイムベストアルバムの記事を読んでください。ロックを含むポピュラー音楽史の中で評価の高いアルバムをランキング形式で紹介しています。
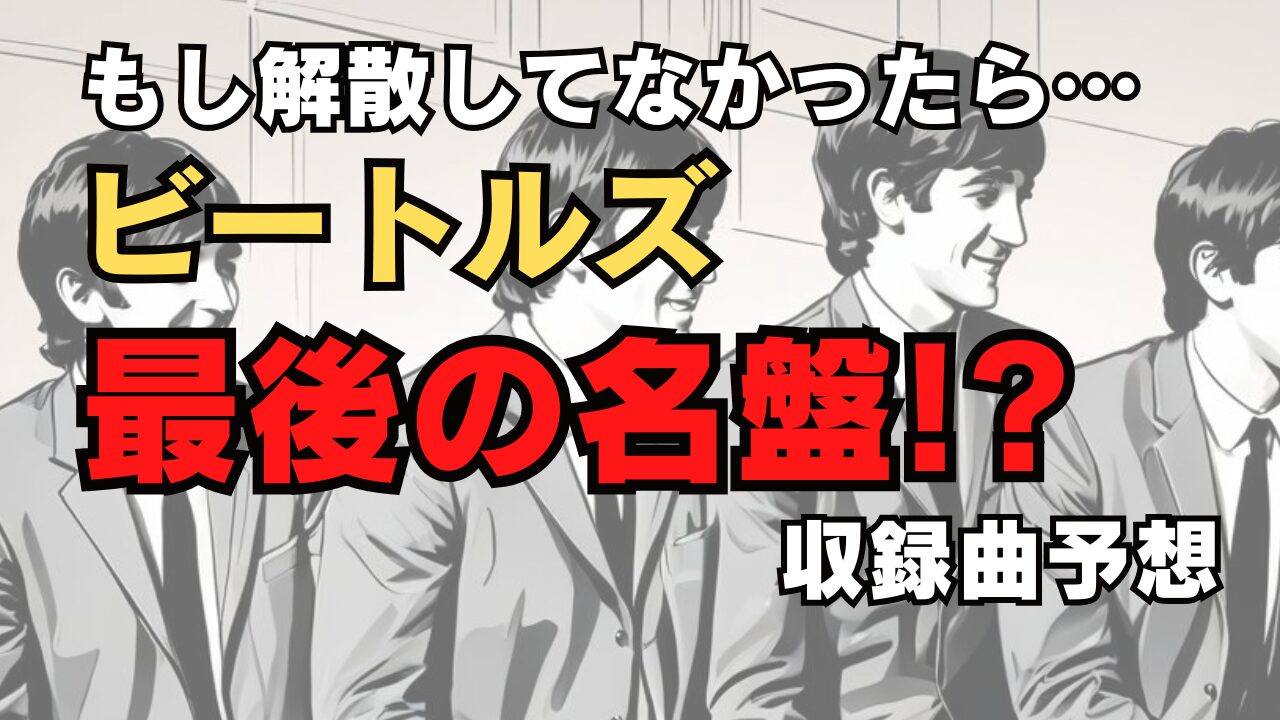
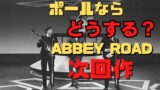





コメント